電波時計 回路説明
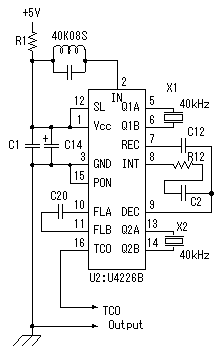 日本の標準時刻電波は福島県のおおたかどや山(40kHz)と長崎県のはがね山(60kHz)の送信所から長波電波として発信されています。今回の装置は40kHzの受信機です。 この電波を受信する機能はU4226Bに全て納められています。外部に取り付ける部品としては受信用コイル、40kHzの水晶発振子が2つ、それといくつかの抵抗器とコンデンサです。 U4226Bは40kHzから80kHzの電波時計専用の受信回路として設計されています。詳細仕様については説明資料を参照してください。 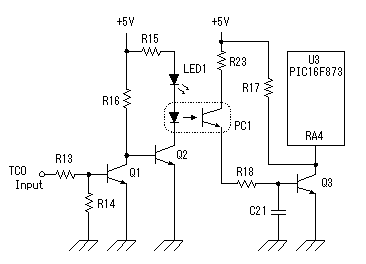 U4226Bの出力信号TCO(Time Code Output)は0V - 5Vのパルスですが、パルス波形の立ち上がり、立ち下がりをシャープにするためトランジスタ増幅回路で信号を増幅しています。 LED1はTCO信号のモニタ用です。電波に乗せられている時刻情報は60パルスで構成され、1秒間に1パルスの割合で送られてきます。各パルスの幅は乗せられる情報により異なりますが、LED1の点滅としては1秒毎に行われます。電波が正常に受けられているかどうかの目安になります。 受信機と表示処理装置をケーブルで接続し、離れた場所に設置できるようにしています。ケーブルを使うことにより途中で雑音が乗ることも考えられるため、フォトカプラ(PC0)を使用して受信機回路と表示処理回路を電気的に切り離しています。 Q3のベースに接続しているコンデンサC21はケーブルに乗った雑音を除去するためです。このコンデンサに大きい容量のものを使用すると立上/立下をシャープしたパルスの波形がなまってしまいます。 TCO信号はPIC16F873のRA4ポートに入力しますが、このポートは他のポートと異なり、オープンドレインタイプになっています。すなわち、PIC内部ではプルアップ(+5V側に引っ張り上げる)されていません。そのため、R17によりプルアップしています。 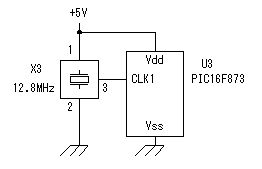 今回の電波時計は電波に乗せられている標準時刻により時刻を表示しますが、電波が途絶えた場合でも正しい時刻を表示させるために高精度の水晶発振子をPICのクロックに使用しています。発振周波数は12.8MHzですからPICの1ステップの実行時間は4/12.8=0.3124μ秒になります。 今回の電波時計は電波に乗せられている標準時刻により時刻を表示しますが、電波が途絶えた場合でも正しい時刻を表示させるために高精度の水晶発振子をPICのクロックに使用しています。発振周波数は12.8MHzですからPICの1ステップの実行時間は4/12.8=0.3124μ秒になります。電波が正常に受信されていればこの発振器の精度は問題になりません。 ちなみに標準電波に乗せられている時刻情報はセシウムビーム型原子周波数標準器などが使われ精度は10-13と言われています。1年間は31,536,000秒ですから317,098年で1秒の誤差が生じるという精度です。そんな先までこの時計を使うとは思えないので、全く狂わないと思って良いでしょう。 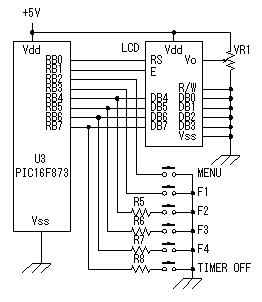 時刻表示、タイマー設定などはLCDディスプレーで行います。今回使用しているSC1602BSLBはデータ転送モードとして8ビットモードと4ビットモードがあります。今回の回路では制御ポートの関係で4ビットモードを使用しています。PIC側の制御ポートにはRBポートを使用しています。8ビットモードで制御するためにはRBポート以外も必要になります。RSは Register Select でコマンドレジスタ(L)とデータレジスタ(H)の切り替え制御端子です。Eは Enable Signal でLCDに情報を読み込ませるための端子です。DB4-7は情報を伝える端子です。また、Vo は Contrast Adj 端子でLCDに表示する文字のコントラストを調整することができます。使用していない端子は全て接地に接続しています。SC1602BSLBにはバックライト機能があります。LCDにはバックライト電源用のA/K端子がありますが、ここに電源を接続する必要はありません。LCD内部で接続されています。 時刻表示、タイマー設定などはLCDディスプレーで行います。今回使用しているSC1602BSLBはデータ転送モードとして8ビットモードと4ビットモードがあります。今回の回路では制御ポートの関係で4ビットモードを使用しています。PIC側の制御ポートにはRBポートを使用しています。8ビットモードで制御するためにはRBポート以外も必要になります。RSは Register Select でコマンドレジスタ(L)とデータレジスタ(H)の切り替え制御端子です。Eは Enable Signal でLCDに情報を読み込ませるための端子です。DB4-7は情報を伝える端子です。また、Vo は Contrast Adj 端子でLCDに表示する文字のコントラストを調整することができます。使用していない端子は全て接地に接続しています。SC1602BSLBにはバックライト機能があります。LCDにはバックライト電源用のA/K端子がありますが、ここに電源を接続する必要はありません。LCD内部で接続されています。RBポートはタイマー設定(時刻設定ではない)のキー入力ポートも兼ねています。RBポートの該当ポートを必要に応じ入力モード、出力モードを切り替えて使用しています。 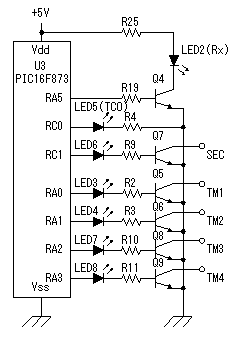 RAポートおよびRCポートを使用して動作状態を表示するLEDの点灯制御と外部回路の制御回路を駆動しています。キットの回路がこのようになっているので、その回路の特徴を説明します。 LED2(Rx)を制御している回路の場合はPICの消費電流を抑えることができます。(5-0.6)V/10k=0.00044=0.44mAの電流で制御できます。 LED5(TCO)を制御している回路の場合は部品点数を少なくすることができます。 SEC, TM1-4の回路は外部回路を駆動しながら駆動状態をLEDで表示する回路です。LEDに流れる電流は(5-2-0.6)V/470=0.0051=5.1mAになります。 キットの回路ではTM3およびTM4にはLEDおよび外部駆動回路が設けられていません。正分用および正時用の回路をTM3およびTM4の回路に使うよう改造をしました。 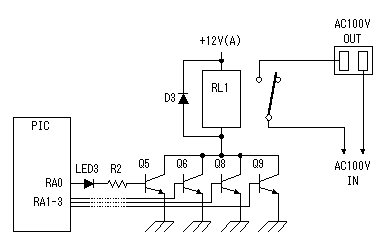 この電波時計には4つのタイマー機能があります。それぞれ独立に4つの装置を制御することができますが、今回の装置では4つのタイマーで1つの装置を制御するようにしました。PICのタイマー機能で制御されるQ5、Q6、Q8、Q9のコレクタを接続した回路でリレー(RL1)を制御します。ですから、同じ日の4つの違う時間に外部装置をON/OFFすることができます。 この電波時計には4つのタイマー機能があります。それぞれ独立に4つの装置を制御することができますが、今回の装置では4つのタイマーで1つの装置を制御するようにしました。PICのタイマー機能で制御されるQ5、Q6、Q8、Q9のコレクタを接続した回路でリレー(RL1)を制御します。ですから、同じ日の4つの違う時間に外部装置をON/OFFすることができます。それぞれのリレー駆動回路にはLEDがあり、タイマーの動作状態を確認することができます。 リレーの電源は電源回路の+12V(A)から取っています。ですからAC入力停止時にはコンデンサによりバックアップは行いません。ACが停止した場合、外部回路へのAC出力も停止するので、リレーをバックアップしても意味がありません。 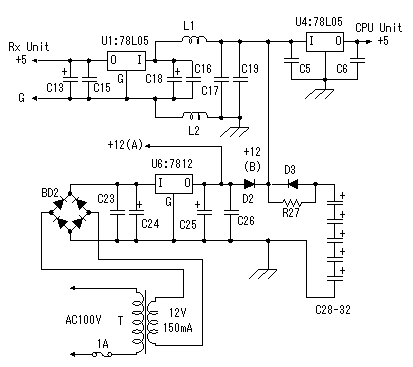 AC入力をトランスを使ってAC12Vに下げた電圧をダイオードブリッジで直流に変換します。AC12Vの12Vは実効値でピーク値はその1.4倍の16.8Vになります。ですから、ダイオードブリッジから出る直流電圧は約16Vの電圧です。これを3端子レギュレータで12Vの安定した電圧にしています。12Vにする目的はコンデンサ(C28-32)の耐電圧のためです。C28-32はAC入力が停止した際のバックアップ用で大容量の積層二重コンデンサを使用しています。しかし、その耐電圧は1つのコンデンサで最大2.5Vです。これを5個直列に接続すると12.5Vの耐電圧になります。この電圧を超えないようにするために3端子レギュレータを使用しています。C28-32の1つ当たりの容量は4.7Fです。5個直列に接続すると容量は1/5の0.94Fです。そのまま充電をすると電源には過大な電流が流れるので、それを防止するためR27を設けています。今回の回路では200Ωの抵抗器を使用し、最大の充電電流は12V/200Ω=0.06A=60mAとしています。充電時間はかかりますが、問題にはなりません。 AC入力をトランスを使ってAC12Vに下げた電圧をダイオードブリッジで直流に変換します。AC12Vの12Vは実効値でピーク値はその1.4倍の16.8Vになります。ですから、ダイオードブリッジから出る直流電圧は約16Vの電圧です。これを3端子レギュレータで12Vの安定した電圧にしています。12Vにする目的はコンデンサ(C28-32)の耐電圧のためです。C28-32はAC入力が停止した際のバックアップ用で大容量の積層二重コンデンサを使用しています。しかし、その耐電圧は1つのコンデンサで最大2.5Vです。これを5個直列に接続すると12.5Vの耐電圧になります。この電圧を超えないようにするために3端子レギュレータを使用しています。C28-32の1つ当たりの容量は4.7Fです。5個直列に接続すると容量は1/5の0.94Fです。そのまま充電をすると電源には過大な電流が流れるので、それを防止するためR27を設けています。今回の回路では200Ωの抵抗器を使用し、最大の充電電流は12V/200Ω=0.06A=60mAとしています。充電時間はかかりますが、問題にはなりません。D2はAC入力停止時にコンデンサからの電流が逆流することを防ぐためです。D3はコンデンサ充電時に充電電流がR27を通るようにし、コンデンサ放電時にはR27をバイパスし、コンデンサの放電電流が負荷に直接かかるようにするためです。 コンデンサでバックアップされた12Vは表示処理装置(CPU Unit)と受信機回路(Rx Unit)に供給され、3端子レギュレータで5Vの電圧に変換されます。受信機回路はケーブルで接続されるため、途中のノイズの影響を少なくするためにチョークコイルが接続されています。 |